藤原新也の21世紀エディション「メメント・モリ」
藤原新也というア-ティストは凄い人である。漆黒の闇を写し取ることの出来る稀有なアーティストなのである。
もはや古いニュースなのであるが、昨年の冬に、彼の代表作「メメント・モリ」の新バージョンが発行された。「21世紀エディション」と帯文に記された当書は、あまり注目されることも無く、ひっそりと書店に並んでいた名著である。
「メメント・モリ」-何度この言葉をつぶやいたことだろうか。すべて思春期に遭遇した藤原新也さんの一冊に依っている。彼岸の国から響いてくる言葉とともに、現代へワープしたかのごとくに写る風景写真のかずかずに、今更ながらに心惹き込まれている。いささかなさけな話であるが、心が癒されたいときなどこの本を開いてみずから慰めていることなど多し。特別なる一冊也。
村上春樹の「めくらやなぎと眠る女」
今日、村上春樹の短編集「めくらやなぎと眠る女」を書店で見つけた。米国で出版された春樹先生の短編集の逆輸入バージョンだそうである。ピンクの装丁が洒落ている。半透明なカバーを被せるなどして手が込んでいる。ペラペラめくって少し考えたものの結局買ってしまった。
早速帰宅電車の中で表題作を読んでみる。20頁程度の短編だから丁度よい長さである。普段何もすることなくウォークマンの音を聴いているより小気味よい緊張感、充実の予感である。そんな心積もりだったのだが、4~5頁読み進めたところで上の空。目は確かに活字を追っているのだが、一向に物語りに入り込むことかなわぬ状態。失態である。こんなことはしばしばあるのだが、こと春樹先生の作品でこんな事態になろうなどとは予想だにしなかったのだから自分自身びっくりなのである。眠気が襲ったわけでもないのに何だろうこの弛緩した感情模様は…。
たぶん以前にもこんな体験はあったのだろうと思うのだ。春樹先生の初期作品といえば、短編作品については特にそうなのであるが、このようなだるい気配を物語の要素としていたことをはっきりと思い出すのだ。だるいというのが不穏当であるならば、ゆるいのである。ゆるい物語の、結末もはっきりせぬような展開を追いながらも、この想像力のユニークさは特筆される。春樹マニアは現在の春樹先生の姿をもまた予想していたのだろうと思うのである。
はらっぱ祭りで「花&フェノミナン」に酔う
毎年この季節になると、小金井の武蔵野公園(通称「くじらやま公園」)でははらっぱ祭りが開催されている。今日は数年ぶりにその祭りに足を運んだ。
お目当ては「花&フェノミナン」バンドのライブを聴くことである。「花&フェノミナン」の出演予定時間は11時50分ということで、休日の家でのんびりする間もなく会場へ。全国各地のライブハウスや祭り会場にてライブ活動を続けて居ることは、主にインターネット情報等にて把握していたのだが、なかなかそれらの会場に、足を向ける機会も減ってしまっていた。
小金井市くじらやま公園の「はらっぱ祭り」といえば、そもそもその昔に、保谷にある「かけこみ亭」に「花&フェノミナン」の押しかけ取材を行なっていたおいらが、初めて彼らの本格ライブに接した場所でもあった。いわゆる格別の想い出の場所なのである。当時は会場の裏地に持参したテントを張り、彼女とテントで一夜を過ごしたりしていたものである。わずか十年ほど前の話なのだが、最近は諸事情(地域住民からのクレーム等)により、そんなことも許されなくなってしまったようだ。祭り自体が縮小傾向を余儀なくされてしまっているようでもあり、さびしいことこの上なし。
昼目前の「花&フェノミナン」出演時間となり、手作り感溢れる特設ライブ会場に人がぞろぞろと集まってくる。この時間に会場に来ている来場者の多くは、バンドのボーカル花ちゃんのファンである。長めの前奏曲が響くと会場前に居た花ちゃんが壇上に立ち登り姿を現わす。定番曲「生まれたよ」のスタートである。アフリカ太鼓のジャンベを打ち鳴らし大地のリズムを奏でているのがさっちゃん。いわゆるMCのパートナーでもある。
あたらし目の曲を挟んで、ラストはこれまた定番の「いのちのうた」。さびのフレーズでは会場の全員が全身でリズムをとって盛り上がりをみせる。会場の壇上を降りた花ちゃんは聴衆の間に駆け込むと、そこには巨大な大地がステージとなって、ダンス会場の舞台といった趣なのである。
実況中継を続けても仕方ないのでこのへんでキーボードを置くが、この野生のリズム、ボーカルに呑まれこむような希少な体験は、これからも度々持ちたいとしみじみ思うのである。
http://www.youtube.com/watch?v=Swa8KMoZJ7E
http://sky.ap.teacup.com/bokurasouko/655.html
村上春樹のノーベル賞受賞はありや否や?
今年のノーベル賞受賞者が発表されて、もう数週間が過ぎてしまった今更なんだ! というお叱りもありましょうが、今日は村上春樹のノーベル賞は有りや無しやといった、我が国の文学関係者・マニアたちがもっとも知りたいと思われる話題に、ちょこっと触れておくことにした。何となれば、某未来のIT長者氏から「最近はブログから『1Q84』が消えてしまいましたね」という、痛いところを衝かれてしまったという経緯が有ったからであり、さらにまたこの時期を逃せば、春樹先生とノーベル賞との話題に触れる機会さえ逸してしまいそうな、そんなびくっとする予感に囚われてしまったからなのである。
結論から述べれば、村上春樹のノーベル賞受賞は「有り」である。日本の文学愛好家にとってはもとより、世界文学界の歩みにとって春樹さんの歩みは凸凹なる関係性をとりながらも接点を維持しているから、受賞の可能性は大と見なくてはならない。もとよりノーベル文学賞といえども、西欧中心のイデオロギー依存にとっぷり浸かっている。過去のノーベル文学賞受賞理由の大半はといえば、西欧スタイルのイデオロギーをどう身に纏った作品であるかが、述べられるばかりであり、今年はさらにその傾向が激しかったためおいらも些か呆れたのものである。そんな逆境を乗り越えるパワーは、春樹さんには備わっているのだろう。期待は大きく持っていくべきなのだ。
現在60歳にして、イスラエルに乗り込むパワーは尋常ならざるものがある。「1Q84」の4部作(3部作ではない)が完成するまであと3年以上先になるだろう予感はあるが、4部作完成の時こそ春樹さんのノーベル文学賞受賞のタイミングに相応しいのである。
青豆と天吾が眺めた二つの月と、再会叶わなかった高円寺の児童公園
 話題作、村上春樹の「1Q84」を紐解きながらページをめくっていると、改めて幾つかのキーワードに突き当たる。物語の終末期において、青豆と天吾がともに眺めて見えたとされる「二つの月」がこれだ。
話題作、村上春樹の「1Q84」を紐解きながらページをめくっていると、改めて幾つかのキーワードに突き当たる。物語の終末期において、青豆と天吾がともに眺めて見えたとされる「二つの月」がこれだ。
河出書房新社による「村上春樹『1Q84』をどう読むか」においても、「二つの月」に関しての文芸評論家なる人々の突っ込みとやらが開陳されていて、それはそれで興味深く読んだのだった。SF小説の基本を踏襲していないだとか、その根拠はどうでもいいたぐいのあれ(!)だが、やはりこう書かれているのを見たりしたら、村上マニアとしては些か内心落ち着かないものがあったので、ちと考え考え、創作してみました。今流行の「フォトショップ」というソフトウェアを使って創作した「二つの月」の出来栄えはいかがでせうか?
少々ネタばらしになってしまうかもしれないがご容赦を。
村上春樹「1Q84」の終末場面での、主人公の二人(青豆と天吾)が、互いに求め合い再会を希求するにもかかわらず、ついに邂逅することの叶わなかったという、重要な舞台設定となった場所である。
杉並区高円寺の南口から歩いて数分、環八通りにも近い場所として設定されているのがここだ。児童公園を見下ろせる六階建てのマンションの一室に、使 命を終えた青豆は匿われている。危険を避けるために絶対に外出を禁じられていた青豆だが、同公園の滑り台に居た天吾の姿を見つけるや居ても立てもたまらず 飛び出してしまった。だが、非情にも再会はならず……。春樹さんも可哀想なことをしてくれたものである。
この滑り台に登って眺めた天吾の視線を想ってレンズを向けてみた。「1Q84」のキーワードともなり得る「二つの月」。二人が、クライマックスを迎 えてどの様に見たのだろうかという興味は、無残にも打ちひしがれた模様。おぼろげに霞んで見えたその月は確実に一つの輪郭を有していた。やはり春樹ワール ドを現実的に理解するのは至難である。
「1Q84」BOOK4に期待する
「1Q84」BOOK3の出版が確実となった今、僕たちが期待するのは、単に第3章としてのストーリー展開だけではなく、総合小説としてのこれからの展開である。ノーベル文学賞候補となって久しい彼だが、真に賞に値する作品を発表していくことを、僕たちは見守っていくべきなのだ。
そのために前提となることは、「1Q84」はBOOK4まで展開されねばならないということである。3部作というスタイルは、総合小説というジャンルに相応しくはない。それは4部作でなくてはならないのである。
世界に目を向ければ、真に総合小説として磐石な評価を受けているものの中に、4部作作品がいかに重要な地位を占めているかが判るだろう。「ジュスティーヌ」「バルタザール」「マウントオリーブ」「クレア」と続くロレンス・ダレルのアレキサンドリア四重奏。鬼才といわれたダレルが才能を開花させ、世界にその名を轟かせた記念作だ。20世紀の現代文学を牽引したジェイムズ・ジョイスの代表作「ユリシーズ」もまた四部作。かつて日本人のノーベル文学賞候補の筆頭とされた三島由紀夫はといえば、「春の雪」「奔馬」「天人五衰」「暁の寺」からなる「豊饒の海」四部作を遺して自害したという経緯も見逃せない。
村上春樹の古くからのファンとして、世界に誇れる総合小説にチャレンジして欲しいなどという我儘な願いを書いてはみたが、実はすでに春樹さんにも4部作があるということを最近知った。初期の「風の歌を聴け」から「1973年のピンボール」「羊をめぐる冒険」「ダンス・ダンス・ダンス」までを「鼠四部作」と称するのだそうだ。初期の作品のテイストはかなり軟派なトーンで埋め尽くされていたという記憶がある。確か「週刊プレイボーイ」(あるいは「平凡パンチ」だったか)に、「春樹先生に学ぶ女性の口説き方」見たいな特集が組まれていて、少年の一時期のおいらはそれらを読みふけっていたものである。
結論は、やはり春樹さんには軟派作家としてではなく、総合小説家としての四重奏作品を期待する。その延長としてノーベル文学賞があるはずである。
村上春樹「1Q84」にみる「リトルピープル」
過日も記したが、現在村上春樹の「1Q84」を読み直しているところである。再読しているのではなく、ところどころ気になる箇所について、その文面を追っている。追いながら、イメージを追体験しているといったところだろうか。
3名に貸し出していたところ、そのうちの1名は家族がらみで回し読みをしていたこともあり、およそ2ヶ月程度のブランクが有ったから、丁度良い追体験になっている。焦らずじっくり、気の向くままに追体験にいそしんでいるのである。やはり一番気になっていた箇所は、「リトル・ピープル」に関するくだりである。何箇所にも及んでいて、その一つ一つにイメージと表現の確認を行っている。
先日、貸し出ししていた友人からの情報で「BOOK3」の件を知ったのだが、彼が示してくれた情報ソースが以下の毎日JPサイトのインタビュー記事であった。
http://mainichi.jp/enta/book/news/20090917mog00m040001000c.html
いろいろ注目に値するインタビュー内容のなかで、最も強調されているのが作家自らの口でリトル・ピープルを解説するくだりだ。彼は語っている。
「はっきり言えば、原理主義やリージョナリズムに対抗できるだけの物語を書かなければいけないと思います。それにはまず『リトル・ピープルとは何か』を見定めなくてはならない。それが僕のやっている作業です」
これほど明瞭な意思表示は珍しいくらいにすがすがしい。世に蔓延る「文芸評論家」なる人種によるたちの悪い妄言をまとめて吹っ飛ばすくらいの意味ある意思表示である。この「リトル・ピープルとは何か」を抜きにした議論ほど不毛な議論はないということを示している。
そしてその序章として示したいのが、数ヶ月来続いてきた、酒井法子へのパッシングに象徴される、無名性の跋扈するパッシングなのである。これについては後日まとめて示していきたいと考えているところである。
村上春樹の「1Q84」について、この作品がジョージ・オーウェルの「1984年」をベースにしているとの指摘は、文藝関係者以外からもことあるごとに打ち出されている。どれくらいの比重があるかないかをはいざ知らず、この指摘を否定することはもはやありえないであろう。
たしかに旧ソ連邦に象徴される高度管理社会は、巨大な悪の権化としての「ビッグ・ブラザー」を想定して議論していくことが可能であった。厳然としてある支配層による管理システムが、明瞭な顔を持って行う権力の行使は、顔の見えるものであった。だが現在においてその図式は成り立たないものとなった。村上春樹さんもその辺のところはとっくにわきまえており、新しい時代を体現する人間たちを「リトル・ピープル」と称したかったのではないか?
「オウム心理教」「ヤマギシ会」などの特定のカルト教団が、そのモデルとして設定されているものの、物語が示しているのは、そんな狭小なものにとどまってはいない。「衆愚の民」と新潮文化人だったらそう呼ぶかもしれない、ある条件に限られた一部大衆にも、「リトル・ピープル」たる資格が備わっているのかもしれない。あるいは、ネット社会における「祭り」に参入して煽り立てるネット流民たち、2ちゃんねる掲示板に群がる匿名ユーザーたちも、その例外であるはずがない。
「正義」の御旗を振り回して「ビッグ・ブラザー」を自称するタイプの人間は周囲に見なくなったが、その反面で「リトル・ピープル」の陥穽におちいっていくタイプの現代人は増えつつある。つまり、一般大衆の多くが好むと好まざるにかかわらず「リトル・ピープル」に変容する環境条件は至る所に散らばっており、そのひとつひとつを検証することに、建設的な価値は見出せなくなっているのである。
村上春樹の「1Q84」について、特にそこで展開されている「リトル・ピープル」に想いをはせるにつれて、彼らに対する拒絶反応とともに、奥深いところではある種のシンパシー、或いは興味深い畏友ではないのか、といった想いを払拭できないでいる。かつて村上春樹さんが著した「アンダーグラウンド」というノンフィクションの最終章を、今宵読み返している。
興味深い一節がこれだ。
「(前略) 私たちが今必要としているのは、おそらく新しい方向からやってきた言葉であり、それらの言葉で語られるまったく新しい物語(物語を浄化するための別の物語)なのだ――ということになるかもしれない。」
新しい物語のモチーフを、ある意味にてオウム真理教のドラマに求めたのかもしれない春樹先生の、肉声を聴いた気がした。
翻って「1Q84」のト゜ラマツルギーにおける「空気さなぎ」の位置づけはどうだったのだろうか? 芥川賞候補作として売り出す経緯やら、最終章(あくまでBOOK2におけるものとしての)で10歳時の天吾と青豆のファンタジーとやらは、現実としての「オウム真理教」体験を浄化させた、新しい物語として、昇華されたものと、受け止め得るのか否か?
藤原新也「黄泉の犬」を読む〔1〕
一昨日の日記に対するコメントで、mimiさんが藤原新也さんの「黄泉の犬」を推薦してくれていたので、ネットで調べてみたところ、つい先日にはその文庫本が発売されたばかりであることを知る。初本の単行本発行が2006年10月であるから、3年2ヶ月ばかりを経ての文庫本化ということになる。それ自体は少しも驚くことなどない。早速、銀座コアという銀座5丁目に聳えるビル内の書店にて購入する。そして帰宅途中の電車内にて読み進めていたと言う訳である。
一読して、ぐいぐいと引き込まれるのである。テーマがオウム真理教に関わる類いのノンフィクション(というか、おいらが好きな言葉で云えば「ルポルタージュ」なり)であることに、二重の意外性を覚えつつページをめくった。第一章「メビウスの海」を読み進めつつ確信するに、これは紛うことなき一流のルポルタージュである。
冒頭のテーマがオウム真理教に関連するのであるから、作者も読者も、また間を取り持つ編集者たちも身構えているのだろうことは容易に察しがつく。さらには、麻原しょうこうの実兄へ、身一つでの突撃取材を試みたりするのだから、話題性も衝撃度も充分である。
思うに、我が国の現役ルポライター(これは和製英語であるからにして、おいらの好きな言葉なり)の誰が、この藤原新也の、ぐいぐい引き込んでいく筆致なりで感動を与える作品を書き得たであろうか? 例えてみれば、一時期は「ニュージャーナリズム」の旗手などとも持て囃されていた吉岡忍の作品のどこが、この一冊に匹敵するくらいのインパクトを与え得るものであったかを問えば、おいらの答えは決まっているのである。所詮、吉岡忍などの書いたものなど取るに足らないものであると。
余談であるがその昔、知ったかぶりの後輩が吉岡忍を称して「ニュージヤーナリズム」を云々した挙句に、「小林さんも読んだほうが良いですよ」と、アドバイスまでしてくれた。そして読んだらもう、その薄っぺらさに呆然としたことなど、蘇って思い出すなり。
という訳にて、今宵のおいらは、第一章「メビウスの海」(p87)までを読み終えると、文庫本を外套のポケットに仕舞い、いつもの行きつけの居酒屋に駆け込んだのでありました。そして酔っ払って帰ってから、本の表紙などスキャニングして、結構大儀な作業なのでありました。
第2章「黄泉の犬」からは、明日以降また気合を入れて読み進めていく覚悟なのです。






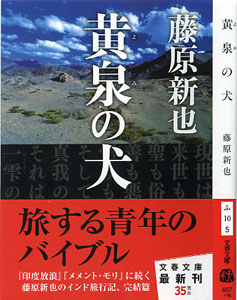
 RSS FEED
RSS FEED