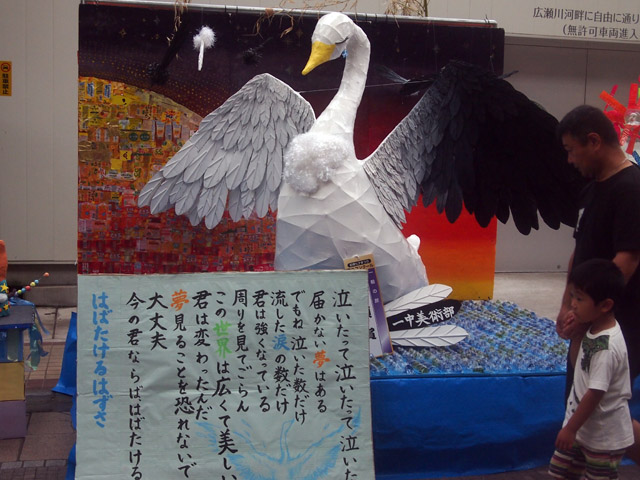「メロかまの煮付け」を食した。「メロ」という魚は一般的には馴染みが薄いが数ある白身魚の中でも大型種で、成魚になるとその体長は1メートルを越えるという。日本に輸入される此の魚は、主にチリ、アルゼンチンなど南米で漁獲される。「マジェランアイナメ」というのが正式名称とされている。少し前には「銀ムツ」という名称で流通していたが、ムツ科の魚とは分類が異なっており、同「銀ムツ」という名前での流通が禁止されたという経緯もある。いわく付きの魚と云っても良い。
大型魚ならではの頭部の食材、カマの料理であり、コラーゲン豊富なプリプリしたその食感が見事の一言だ。煮付けの味付けはオーソドックスな和食ならではだが、外来魚としてのメロの食感が、何故か新しい。酒の肴にももってこいなのである。