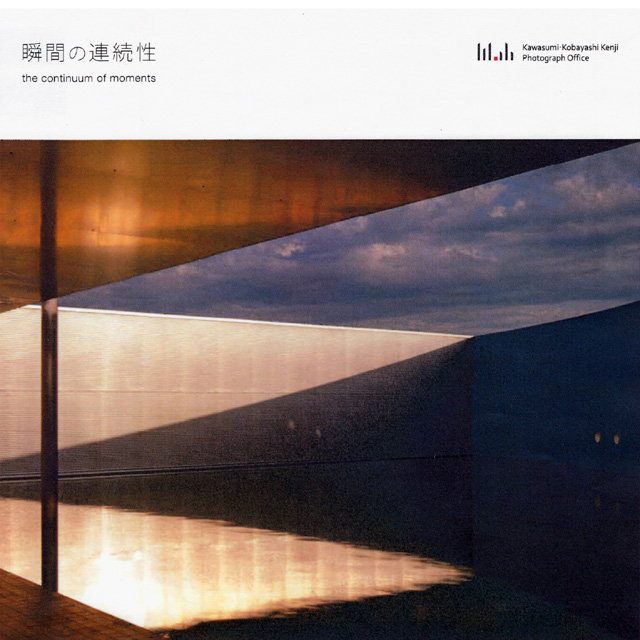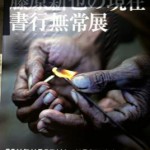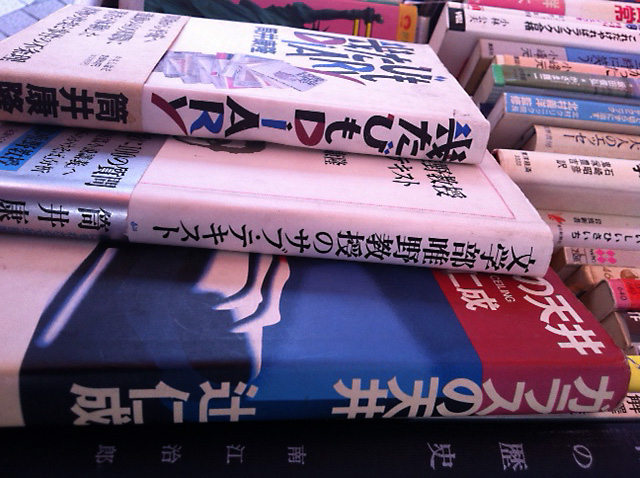[エラー: isbn:9784062175616:l というアイテムは見つかりませんでした]
芥川賞受賞作こと円城塔氏の「道化師の蝶」を「文藝春秋」誌の最新刊にて読了した。だが然しながらであるが、実は今回は、言葉を失っている。感想はおろか、作品分析の取っ掛かりさえ掴めないような、ある種の言葉を失っているような状態なのである。
タイトルとなった「道化師の蝶」には、「道化師」「蝶」といった云わば想像力を存分に刺激するべき語彙的要素を有したタイトルではあるが、然しながらそんな想像力やら期待やらを抱いて書物にのぞむと完全に裏切られてしまうことが請け合いである。
それはまるで、言語を無に帰する壮大な試みなのかとも感じ取らせてしまうくらいである。果たしてそうなのであれば、円城塔氏は途轍もない天才作家と云うことにもなろうが、そんな作家が居るのかどうか、存在可能なのかどうかさえ、覚束ない。
芥川賞の今回の選考委員会は、村上龍の「限りなく透明に近いブルー」受賞時のそれほどではなかったにしろ、そこそこに紛糾し揉めたかのようである。「選評」を読む限り、積極的に推した選考委員は居なくて、初回投票にては過半数にも達しなかった。通常はこれで選外となる運命なのだろうが、今回は特別に、主宰者である文藝春秋社側の特別な要請で、再度の受賞討議が行なわれて、結局のところはそこそこ揉めた末に受賞作品となったとのこと。
「支持するのは困難だが、全否定するのは更に難しい、といった状況に立たされる。」(黒井千次氏評)
「〈着想を捕える網〉をもっと読者に安売りしてほしい。」(山田詠美氏評)
「この作品だって、コストパフォーマンスの高いエンタメに仕上がっている。二回読んで、二回とも眠くなるなら、睡眠薬の代わりにもなる。」(島田雅彦氏評)
「これは小説になっていないという意見もあれば、読んだ人たちの多くが二度と芥川賞作品を手に取らなくなるだろうと言う委員もいた。賛否がこれほど大きく割れた候補作は珍しい。」(宮本輝氏評)
「『道化師の蝶』なる作品は、最後は半ば強引に当選作とされた観が否めないが、こうした言葉の綾とりみたいなできの悪いゲームに付き合わされる読者は気の毒というよりない。」(石原慎太郎氏評)
「今回の『道化師の蝶』で初めて私は『死んでいてかつ生きている猫』が、閉じられた青酸発生装置入りの箱の中で、なゃあ、と鳴いている、その声を聞いたように思ったのです。」(川上弘美氏評)
川上弘美氏は好感度を込めて選評を記しているが、戸惑いの評をもまた綴っている。川上さんは授賞式にて「二人のカメレオン」と受賞作家を称揚したという。川上さんのそんなコメントを確認してから、もう一度この受賞作品と向き合って行きたいと思うのである。