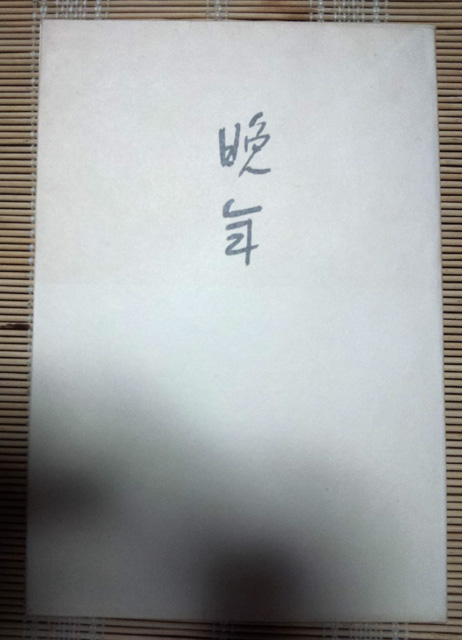[エラー: isbn:9784062180320:l というアイテムは見つかりませんでした]
気鋭の若手芥川賞作家こと平野啓一郎さんが著した新作の「空白を満たしなさい」を読了した。最初はみるからに人生訓的な匂いを発する同書の表題に引かれて手に取り、目次等に目をやりつつ、そのまま購入することとなっていた。
家族としての最も近しい身内の死や、関係する身内近親者の死者への対応等がテーマである。そもそも人間の「死」については、おそらくは人間である限りは誰もが考えあぐねる究極的テーマであり、この究極的テーマの設定に加えて、SF的エンターティメント的な設定に、最大限の興趣をそそられていたのであった。
何しろ購入したもう一つの重大な要素は、「復生者」、すなわち一度は死んだ後に生を受けて復活したという人々の集団が、重大なプロットとして設定され、ドラマが織り成されていくことが想定されていたからであった。生き返った男が、ドラマの重大な物語的設定の中で生きて、本来的な生者たちの心を掻き毟っていく、のである。エンターティメント的設定としては、これ以上無いくらいに満タンに整っている。
主人公的登場人物であり、死から生き返った設定の土屋徹生は、自分が自殺によって死んだということに納得できないでいた。事故死でもなく、殺人であるはずだという思いから、自分を殺害した殺人犯を追及していくのが前段である。然しながらその思いは打ち破られていき、自分が自死、自殺を図ったことを確認して唖然とするのだ。残された妻と子供に対する懺悔の気持ちと共に、自らの死について、検証しながら自問する日々が待っていた。
中盤の設定としては、自死した自分自身の葛藤に煩わされつつ、家族との絆を取り戻そうとしてもがく主人公がいる。人生訓的表題に対応する展開ではあるのだが、当該的展開は非現実的要素に満ちてあり、プロットも中だるみのロットも印象がぬぐえない。
終盤に来て物語は最後の盛り上がりに達し、其処でこの物語が示した世界観を、厚い筆致と共に受け入れることとなっていた。前段、中段の物語のプロットが非現実的夢想的であったことを残念に感じたものだが、終段の展開に心躍らせていたのだった。