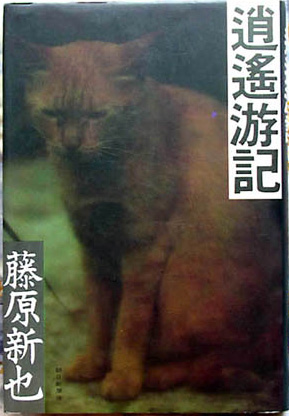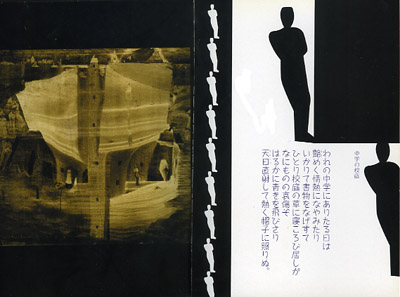[エラー: isbn:4048740245 というアイテムは見つかりませんでした]
「文士料理入門」という新書を読んでいる。新書版ながら定価1000円(税抜)という、些か高価な買い物をしてしまった。何故おいらは、あるいは人は、文士料理なるものに惹かれてしまうのだろうか?
「文士料理」と一言で括って語るのは難儀である。肉食系、菜食系、等々と云った共通の趣向性がある訳でもなければ、文士の人生哲学が料理に反映されているという訳でもない。しかしながらどこか懐かしい。たとえ初めての料理であってもひじょうに郷愁をそそるのである。
そんな郷愁を感じるのは、幼少期に過ごしたであろう豊かで無尽蔵な時間というものを、そこに感じ取っているからなのだろう。坂口安吾先生のメニュー「わが工夫せるオジヤ」では、3日以上煮込んだ野菜ぐつぐつスープが無くては始まらないという特性オジヤを開陳している。3日煮込んだスープとはどんな味わいなのかと、創造するだに待ち遠しくなってくる。そんな時間を持てたら嬉しい。最近はそれ以上の贅沢は無いと想えるくらいに。
たとえ物は無くてもあり余るくらいに無尽蔵な時間というものが、そこにはあったのだろうと想うのである。ハンバーガーなどと云ったファーストフードではこのような豊かな時間を味わうことは決してできないのである。
あえて共通の基本点を探れば、インスタント調味料などは使わないということである。味の素ファンであるフルちゃんはこうした意見に反論なのだろうけどなぁ(笑)。