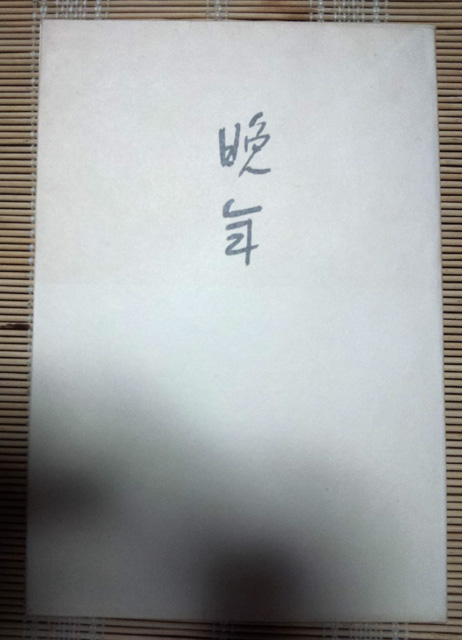銀座のレポートは昼に偏っていて、夜がなかったことに気付いたのです。そこで、以前おいらが某メディアにて記したレポートをアレンジして、銀座の名店「ルパン」について紹介します。

坂口安吾が愛した「ゴールデンフィズ」
先日、銀座にある老舗バー「ルパン」に行ってきました。昭和3年に開設されたこの酒場には、太宰治、坂口安吾といった無頼派作家をはじめ、数多の作家、芸術家たちが足を運んだ社交場としても有名で、今なお彼らの足跡を辿るべく全国からのファンが訪れているそうな。少年の頃から太宰さんや安吾さんを敬愛してきた僕が、今頃になってここを訪れたのは遅きに過ぎたのですが、これも銀座勤めがもたらした巡りあわせなのかも。遅れて叶う出会いというのもまた乙なものでした。
何もわからないまま、安吾さんが好んで飲んだという「ゴールデンフィズ」というカクテルを注文してみました。ジュースに卵黄を入れてシェークしたものらしく、結構甘口系で、辛党の僕としてはとてもお酒を味わった気分にはなりません。銀座では銀座の酒をということなのか。無頼派の旗手こと安吾さんも案外銀座の振る舞いを熟知していて、人生と作品探求にも熱意がこもったのでしょうか。ちなみにこの日、何故太宰さんの愛飲した飲み物を頼まなかったかといえば、太宰さんは一流の道楽者ですから、きっと予算オーバーしてしまうこと必至であり、その点で、危険な香りを振り撒く女豹より、いささか口煩いが安心してつき合える堅実派の安吾さんによりシンパシーを感じていたためなのかもしれません。
よく知られているように、ここには林忠彦が駆け出しの頃に撮影した写真が展示されており、大きく額装された中には、一寸地味目にカウンターにおさまる安吾さんの姿もありました。林忠彦は当時「ルパン」を自分の連絡場所としていて、ここで知り合った安吾さんの住居に押しかけては、ごみだらけの仕事部屋で撮影した写真を発表して、話題をさらったものでした。のちにそれらの写真は「カストリ時代」という写真集にまとめられ、戦後の昭和二十年代を伝える貴重な一冊となっています。
「カストリ」とは粗悪な密造酒のことをいう。林忠彦が出会った当時の安吾さんの自宅では、時々仲間を集めては「カストリを飲む会」が開催されていたそうです。安吾邸にはカストリの入った石油缶がでんと置かれていて、それを仲間に振舞っていたというのだが、自分は「ルパン」でゴールデンフィズを愛飲していたのだから、安吾さんがはたして「カストリ」を好んでいたのかはなはだ疑問です。酒乱で鳴らした太宰さんや織田作と違い、安吾さんが泥酔する姿はあまり想像できません。仲間たちには安物の密造酒を飲ませつつ、こっそり高級酒をちびちびとやりながら推理小説のトリックを練っている。そんな安吾さんの姿を想像してしまうのです。それこそが無頼派の旗手として混沌の時代を駆け抜けた安吾さんの生き様ではなかったのではなかろうか。
それにしても「カストリ時代」とは粋なネーミングである。現代ならばさしずめ「発泡酒の時代」とでもいうのだろう、どうもピンとこないし味気ない。「ハイボール」の人気が上昇中だが、「ホッピー」ほどには人気定着の兆候は見られない。粋で天晴れなネーミングはないものかと悩む毎日である。
考えてみれば時代を表わす酒、あるいは時代のキーワード、ネーミングとはとても難しいものである。現在のマスコミが多用する「ネットの時代」「未曾有の時代」なんて全然駄目である。対抗できるのは一昔前に椎名誠が命名した「かつおぶしの時代」くらいじゃないかなと思うのであります。芸術作品は「時代を映す鏡」ともいわれるが、なかでも写真ほどこれに当て嵌まる媒体はないと云っていい。「現代」「今日」といった時間を写し取っているのだから当然のこととはいえ、時代の息吹を見事に活写した林忠彦や坂口安吾さんの取り組みには、益々畏敬の念を禁じ得ないのである。