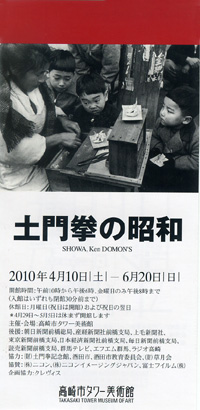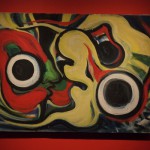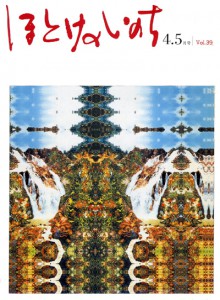高田渡さんの音楽が大好きというデュオ「ハッピー★ホッピー」のライブイベントに、昨日遭遇したのです。
そのライブは吉祥寺の「のろ」というお店で開催された。高田渡さんの名曲「ヴァーボン・ストリート・ブルース」からスタート。ボーカルのりかさんは、洒落たウクレレを小脇に抱えながらリズミカルなメロディーを奏で響かせる。あまり広くない会場は、この日「15人限定」と銘打って行なわれていたのだが、あたかもホームパーティーで口ずさむ様な独特のノリがとても手応え強く、ガツンと響いてきたのだ。元はジャズシンガーだという彼女の歌声は会場を響き渡りながらてらいがない。本物である。先日伊豆で聴いたお姉ちゃんシンガーたちとはえらい違いである。かつてりかさんは、渡さんの行き付けの焼き鳥屋「いせや」に、社会勉強のために足を運んでいたことがあるという。気合も中々充分なのである。
高田渡ナンバーだけではない。オリジナル曲も沢山あって披露していたが、独特なテンポのあるリズム感やフレッシュでユニークな歌詞の世界観などをみせていて、とても素敵なのである。少し前の5月には記念すべき「ハッピー★ホッピー」の初アルバムが発売されている。その中の幾つかをピックアップしてみる。
以下、ファーストアルバム「ハッピー★ホッピー」より
「ホッピーあります」
ホッピー大好きなおいらも好きな応援歌。「ホッピービバレッジwithキンミヤ焼酎」の公式応援歌を目指している。
「キララ☆恋の歌」
昔はよく歌っていたという、デュオの代表的な恋歌。20世紀後半のリカさんの乙女時代から恋の棚卸し曲!
「ギターおじさん」
愛すべき高田渡さんを思ってつくられた曲。
♪ くしゃくしゃな笑顔で
ぴっかぴかな歌を歌う
噂の町の煙の中
いつでもたたずんで …
♪
ぜひ聴いてみてください。
http://happyhoppy.pepo.jp/movie.html
会場には小室ゆいさん(小室等さんの娘さん)、サックスの武田和大さんも駆けつけていた。2部ステージではりかさん&ゆいさんのハーモニーが響き渡り、ライブはとてもアットホームな盛り上がりをみせていたのです。
という訳で、昨晩は素敵な音楽にどっぷりと漬かった夜であった。その心地よい余韻は今も尚、続いているようなのである。